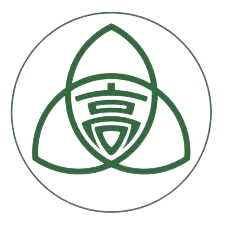ニュースNews


2025/01/14
「流れ星」について
こんにちは、天文部の宮良です。
冬休みも明け、一月も中旬に差し掛かる頃ですが寒さは一層深まるばかりですね。このような寒さでは夏が恋しくなります。夏と言えば星についても多くの星座などが見れますが、今回は「流れ星」と関連する「彗星」について書いていこうと思います。

画像:ペルセウス座流星群(2016年)
実のところ、流れ星は俗称であり正式名称は「流星」といいます。流星は地球の大気に流星物質が突入することで加熱され、輝きながら消滅する現象と定義されています。流星の原因である流星物質は彗星や小惑星から放出されたチリであり、基本的には彗星から放出されたものが大体の流星の基になっています。特にペルセウス流星群などの流星群は、彗星の軌道上に残った流星物質に地球の公転が重なることで発生しています。
また、流星が光るのは0.3秒程度であり、願い事を叶えるために3回言うには0.1秒ごとに一回言わなければならず、とても難しいことがわかります。
読者の皆様にも流星の概要が分かったところで有名な流星群を三つ紹介したいと思います。

画像:ペルセウス流星群(2007年)
始めに紹介するのは、ペルセウス流星群です。8月の12~13日頃に活動がピークを迎えます。ペルセウス座付近を中心として流星が流れるため、流星群の命名規則に則ってペルセウス流星群と呼ばれています。また、この流星群の基になった流星物質は約130年周期で太陽を公転しているスイフト・タッフル彗星が軌道に残したチリであり、この彗星がこの流星群の母天体になります。

画像:ふたご座流星群
次に紹介するのは、ふたご座流星群です。12月14日頃に活動がピークを迎えるふたご座付近を中心とした流星群です。正確には、完全なピークを迎える時間では日本は昼間であるため完全の状態では観測できません。母天体はかつて彗星だったフェートンという天体です。

画像:しぶんぎ座流星群
最後に紹介するのは、しぶんぎ座流星群です。1月4日の明け方がピークであり、うしかい座とりゅう座の境界付近で観測が可能です。名前の由来はうしかい座とりゅう座の境界付近にかつて設定されていた壁四分儀座という星座から来ています。母天体は特定されていません。
いかがでしたか?
流れ星一つとっても壮大な世界が広がっていることがわかりましたね。この記事で流星に対して興味を持てたのなら幸いです。
画像引用:国立天文台 ペルセウス座流星群 2016 https://www.nao.ac.jp/gallery/weekly/2016/20160913-oao.html
:AstroArts https://www.astroarts.co.jp/news/2007/08/15perseids/index-j.shtml
:AFPBBnews https://www.afpbb.com/articles/-/3443340
:天体写真ギャラリー https://www.astroarts.co.jp/photo-gallery/photo/59527
研究成果を掲示しています!
|
光と宇宙